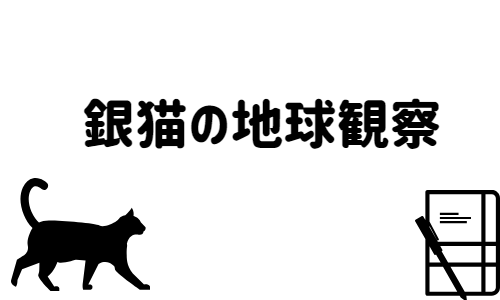猫です。最近読み終えた本の中で、特に印象的だった「地下室の手記」について感想を残します。
(自分の心理状況や経験で感想が変わりそうなので)
理解を深めつつ時間が経ってからも思考を追えるように、自分用の解説と引用をしつつ、気になったところをピックアップします。
地下室(哲学的ターン)
まず、主人公は親戚の莫大な遺産によって現在は地下室にこもりっきりの生活をしています。
かつては役所に勤めていて、しかし賄賂は受け取らなかったと独白が続きます。
かといって、規範重視の人物というわけでもなく、はっきりと「人間は欲望(衝動)を重視するべきだ」と述べています。
人間に必要なものは 、ただ一つ 、自発的な欲求のみである 。その自発性がいかに高くつこうと 、その結果 、どこに行き着くことになろうと 、かまやしない 。
作中全体を通して自暴自棄な人物だな、という印象を受けましたが、比較的最初に出てくるこの一文からにじみ出ているように思います。
欲望の分析
この前半の独白の中で私が特に気になったのは、彼が欲望について色んな角度から分析しているように見えることです。
それらはさまざまな古典作品を引用していて、次の読書の足がかりにもなりそうでした。
たとえば、こんな感じ。
人間そのものが 、ピアノのキ ーかオルガンの音栓のようなものに過ぎないのだ
この言葉はディドロ(フランスの思想家)の引用です。
ドストエフスキーは1840年代に青春を過ごした人で、この主人公も同年代生まれの設定のようです。
歴史的背景については割愛しますが、この世代は西欧文明の影響を強く受けています。
主人公自身もちょくちょくフランスの書物を引用し、そして彼が揶揄する対象(コミュニケーション能力が高く、円滑に物事を進めるやり手タイプ)も発言中にフランス語の言い回しをはさみます。
これは、主人公もやり手タイプも同じインテリタイプで、しかし立場が大きく違うことを表しているように思いました。
先程の衝動を重視する発言にはこう続きます。
なにしろその欲求だって、そもそもいかなる代物かしれたものではないのだから…。
それからさらにこう続きます。
「ハハハ !そもそも欲求なんてものが 、本当は 、まあ強いて言えば 、存在しないのかもしれないじゃないか!」と、あんた方は高笑いをしながら口を挟むだろう。「このごろは、科学が人間を解剖し分析を進め、今の時点でもすでに我々にとって明らかなんですよ。欲求やいわゆる自由意志などというものは、まさに…」
そして欲求の分析が進めば人間は何かを欲求することをやめるだろうと言っています。
「誰が好きこのんで対数表どおりに何かを望んだりするものか」と。
この予想から時代が進んだ現在、人間の欲求は分析が進みましたが、むしろ人の欲求は加速しているように思います。
現在の情報社会と、彼の想像した未来が大きく違うせいかもしれませんが。
一方で、緻密に設計された「欲求を高めるための仕掛け」をよく思わない声や、ネタばらしを行う動きもあります。
この関係は、交霊術が流行した時代にフーディーニが行ったことに似ていると思います。
地下室の住人とは
2章からは回想形式で読みやすく、主人公の人となりを知ることができます。
私も、前半では感じられなかった親しみを感じることできました。(もちろん嫌悪感も)
決闘
主人公がまだ地下室に籠っていなかった頃の話です。
ある晩バーでケンカをしているのを見かけ、窓から放り出された男に羨ましさを感じます。
その割に、ある将校に押しのけられたことに腹を立て、いつまでもそのことに怒っています。
やり返してやろうと計画し、人目を気にして有り金をはたいて身なりを整え、しかし将校を目の前にするといつも道を譲ってしまう。
ようやくやり返すことに成功したが、相手は特に気にしていない様子です。
主人公は「そんなふりをしただけだ」と思い、「対等な立場になった!」と有頂天です。
・感想
基本的にすごく粘着質な人だという印象です。
特に、このエピソードにあるような「侮辱された」という思い込みがひときわ目立ちます。
そしてその執着のために、有り金をはたいて服を新調するなど見栄を張ります。
しかし、実行しようとすると怖気づき、はっきりしない最後を成功したことにして納得します。
理想は高く、思い込みが強く、手段は選ばないくせに、実行力がない姿です。
旧友の輪に混ざれない
主人公はこの頃も人付き合いのよい方ではありませんでしたが、発作のように突然、人恋しくなって友人を尋ねるクセがありました。
訪ねた友人宅で「学生時代に憎んでいた同級生が引っ越すこと」「友人たちがその送別会を開くこと」を聞きます。
彼は手持ちの金がなく、そして特に好きな相手でもないのに勢いで「俺も行く」と言ってしまいます。
しかし、当然ながら歓迎されていない主人公は嘘の時間を教えられて待ちぼうけになり、会が始まってからはキレまくりです。
人付き合いの下手っぷりと横暴さにより、同じ部屋にいるのに除け者にされてしまいました。
・感想
主人公は学生時代からあまり友人の輪には溶け込めず、そのかわりに勉強に打ち込み、成績は良かったようです。
しかし、結果としてそれは「自分は賢い(だからあいつらとは話が合わないんだ)」という傲慢さを加速させているように感じました。
この傲慢さは本編中に何度も描写されています。
なかなか惨めな気持ちになりますが、共感する姿もあるエピソードです。
たとえば「普段は人を嫌っているのに突然人恋しくなる」ところです。
普段から親しくしていない人々の集まりに飛び入り参加して温かい対応なんて期待できるはずがありませんが、主人公は期待して飛び込みます。
結果的に、過剰に期待して、過剰にがっかりすることになりました。
コミュニケーションが苦手な人はすごく覚えがあると思います。(少なくとも私はそう)
このエピソードはグルーミングが下手な動物が群れの中で孤立している様子が目に浮かびました。
動物は毛づくろいで交流しますが、普段から他の個体に毛づくろいをしない個体には誰も毛づくろいをしてやらないそうです。
ヒステリー
先程の送別会が終わり、友人たちは二次会に移動し始めます。
主人公はもううんざりしていたのに、ここでも「俺も行く」と言ってしまいました。
手持ちの金がないので友人に無心し、投げつけられた金を拾い、二次会会場の非合法の売春宿に行きました。
そこでリーザという女性に会い、彼女をストレス発散に使います。
主人公自身おそらくそんな経験はないのにあたたかい家庭などの理想を語りまくります。
本の知識から語ったためか夢想家のせいか、リーザに「まるで本を読んでいるみたい」な喋り方と言われ、傷つき、その後は罵りまくります。
しかし、なぜかリーザは主人公の言葉(罵り)に共感し(洗脳されやすいのか?)主人公はここでも意に反して自分の住所を渡してしまいます。
後日、主人公が自宅で従者に邪険に扱われているところに、リーザが訪ねてきました。
主人公はそれまで「リーザは俺を英雄視しているに違いない」と思っていたので、惨めな姿と貧しい暮らしを見られて大ショックです。
理想と現実のギャップにヒステリーを起こし、哀れんでいたリーザに憐れまれることになりました。
最後に意地の悪い思いつきとして、別れ際のリーザに金を握らせますがあっさりと見破られて突き返されました。
主人公は激怒して追いかけましたが、リーザはもうみつかりませんでした。
後味が悪いのでこの日記は終わりにしようかな、という言葉で終わります。
・感想
説教の時点で非常に嫌な感じですが、いつの時代もこういう人はいるのでしょう。
本の知識や夢想から理想を語っているのが印象的でした。
また、一人称の語りなのでわかりにくいのですが「リーザが英雄視している」のは主人公の思い込みという可能性があります。
2番めのエピソードと同じ過剰な期待と過剰ながっかりですね。
従者に嫌われているのは、理想が高くて実行力のない人間の実態をよく知る人間の反応とも言えそうです。
最後に金を渡したのは、おそらくリーザの愛にうまく応えられず、侮辱で返そうとしたのだと思います。
愛に対して金を渡すことで「売春婦として愛を買ったんだ」「金ならあるんだ」という意味になるのかな、と。
ちなみに、有名な一杯の茶~の文です。
俺が必要としているのは 、平穏無事というものだ 。自分さえ無事でいられるなら 、今すぐにでも全世界を一コペイカで売り飛ばしてやる 。世界が破滅するか 、それとも俺が一杯の茶を飲めなくなるか ?というなら 、はっきり言っておくが 、自分がいつでも好きな時に茶が飲めるためなら 、俺は世界が破滅したって一向にかまわない
この地下室の住人と時間をかけて付き合ってみた結果、この文が茶のおいしさを伝えるものではないとわかりました。
これはヒステリー中の文ですし、彼の自暴自棄さと「意識的無気力のほうがマシ=だから地下室にこもる」というスタンスを表しているだけです。
茶が飲めることが平穏さの象徴になっているので、そういう文脈としては使えそうです。
余計者
この主人公は地下室の住人です。
言動が支離滅裂なので地下室の住人とはなんなのか?ということがわかりにくかったのですが、あとがきの解説を読むとこういうことでした。
人物背景としてこんな感じ。
- 主人公は1840年代に青春を過ごした40年代人(ドストエフスキーもそう)
- ペテルブルグに住み、改革による西欧文明の影響を強く受けた(ロシアインテリゲンツィアの流れを汲む)
- 主に書物から西欧の思想や芸術を取り込んだ
- 理想主義者でロマンチスト
そして↑の人々の中から余計者が生まれました。
余計者というのは、
高邁な理想を胸に、全人類の福祉のために奉仕したいという願望を持ちながらも、いざ実行という段になると何一つ成し遂げることができない。漠然と全人類に向けられていた愛情も、生身の身近な個人の愛には決して応えることができないのである。
たしかに、彼が同級生を揶揄していること、同級生は社会的に成功していること、
そして少なくとも学業の面で彼は同級生に勝っていたことなど、丁寧に描写されていました。
地下室の手記という作品も非常に身につまされる作品でしたが、この解説の鋭い分析が何より刺さりました。
全体の感想
一見すると支離滅裂、ジェットコースターみたいな情緒不安定です。
でも、整理してみていくと、結局これは
- 彼自身が夢想家であること
- 夢想家で理想主義なため、何事にも期待しすぎてしまうこと
- 期待が大きいせいで普通の現実にも非常にがっかりすること
によるのではないでしょうか。
想像と意気込みばかりで実行しないせいで、理想と現実のギャップが埋まりにくいのかな、と思いました。
経験を重ねた人って「まあこんなものかな」という諦めに似た分別がありますよね。
でも、彼はいつまでも実行しないので経験を積んで諦めの精度を高めることができません。
たとえば、2章の最初のエピソードでは
- 復讐がうまくいくことを想像する
- 実際にはやり遂げられない
- やり遂げていないけど「できた」「あいつは悔しがっているはず(想像)」
という結果になっています。
もし彼が勇気を出して本当にやり遂げていたら、現実(将校の反応)はもっとはっきりとした形で目の前に現れていたはずです。
その現実は彼を傷つけるでしょうが、理想との差を実感することにより、次回の想像はリアリティを増したでしょう。
私はそれがたぶん人生経験というものだろうと推測しています。
結局、彼が「余計者」から「やりてタイプ」になり、感情面での平穏を得るには、
夢想を実行に移すか、夢想をやめる(あるいは規模を小さくする)ことでショックを減らす、
しかないと思います。
しかし、現在の彼は冒頭で紹介されていたように莫大な遺産(第三の選択肢)を得て、仕事を辞め、地下室にこもっています。
晴れて気ままに生きられる生活を手にしても、知識があるせいか不安があるせいか、
「規範に従わねばならない」という理性と「欲望に従って生きたい(衝動重視で生きたい、その代償がいくら高くつこうと)」
という葛藤は続いているように見えます。
結局彼を苦しめていたのは、理性や社会的規範ではなく自分の考えた規範(理想)なのではないか、と感じました。
彼の考え方は苛烈ですが、この起伏をもっとなだらかにすれば、私にも身に覚えがある事ばかりです。
一つの作品の中に凝縮されているものを読むと横暴すぎて不愉快でも、切り離した事象では多くの人が共感できると思います。