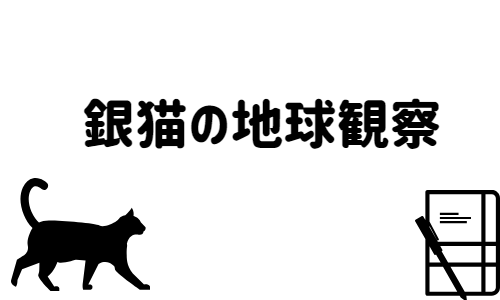今日はなんだかぐずぐずしてしまい、通院は午後診になった。
たぶん寝不足のせいで起きられなかったんだと思う。
月末のことがあるし、あんまりお金を使いたくなかったけど体験欲を満たしてリフレッシュしたかった。
なので、図書館に行った。
まず、気になっていた本を探しに行った。
この本は、凡庸な私が「どういうこと?」と思っていた部分をわかりやすく解説してくれていた。
たとえば、カントの言う「物自体」とかショーペンハウアーの言う「意志」って結局どういうことで、なんでそういう発想が出てきたのかな?ということ。
特に、時代背景を添えて民衆の在り方を噛み砕いて教えてくれたのが面白かった。
倫理の項目は特に興味深かったのでメモから抜粋する。
たとえば、
- 19世紀の急激な産業化が神によって象徴されていた人間相互の信頼関係を崩壊させた
- パリやロンドンの万国博覧会が植民地支配を正当化した(欲望を肯定)
- (同じく)万国博覧会で消費的な財やサービスが浸透
など。
そのまま消費社会論へと続く。
消費社会論は割と「そうやな」「せやな」の連続だし、みんなもう知っていることかもしれない。
この時代から忠告はあったのに意志に抗えなかった(あるいは抗う気すらなかった)ということだろう。
ヴェブレンの
消費はもはや自然的な欲求ではなく地位や富を誇示する顕示的な欲望
という言葉などは、昔の人より現代人に鋭く刺さるかもしれない。
私が特に「なるほど!」と思ったのは、3の万国博覧会による消費の浸透について。
これは以前、ベルエポックについて調べていたときに引っかかっていたポイントだった。今回で少しわかってきた気がする。
また、時代背景(第一次世界大戦・フランス革命など)を知ると、自殺論についての解釈も大きく変わる。
たとえば、冒頭に述べられている
「真剣な闘争などありはしない」「どんな事件が起ころうとも、むきになって考える必要はさらに無いのだ」
という節を私は己の葛藤や不条理の話だと捉えていたが、時代背景を加味すると戦争や恐怖政治のことではないかと思った。
ショーペンハウアーのいう自殺は(「自殺について」内でも述べられているとおり)失恋や人間関係の悩みの末のものではなく「われとわが生きようとする意志との破綻」だ。
19世紀後半のペシミズムというのは、おそらく現代の私が考えるペシミズムとは違う。
どうしようもない障害と生への意志があったのだろう。
生きようとする意志は、死を願うという形をとって、いよいよ明らかに現れ、その極端な表現が、すなわち自殺である。
という言葉の意味がようやくわかりそうだ。
その苦悶と比べると、私はまだ破綻していないのかもしれないと思った。
それから、共苦の倫理学。
産業化以前、人々は「欲望のままに振る舞うことが共同性崩壊の根源」だと理解していた。
消費社会論での「己を律するために神という恣意性や暴力性から離脱した存在の象徴をつくっていた」ということと合わせると、ショーペンハウアーの言う『真の世界』は産業化後の世界の暴力性を批判するための装置のようなものなのかな?と読み取った。
つまり、真の世界が本当にあるかどうか・ここが表象の世界かどうかは問題ではないということだ。
「来世のために徳を積んでおく」に近い考えだと思う。来世があるかどうかは大した問題ではなく、人々を律するための仕掛けということだろう。
共苦の倫理学とペシミズムについて興味深かったので、また図書館に行って続きを読もうと思う。